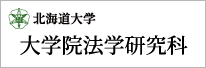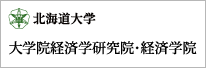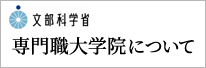学生の提言活動
2024 年度 政策討議演習 (古平町班)
活動報告

2024年5月、北海道古平町役場より、外部の視点から地方創生をテーマに政策を立案してほしいとご提示をいただきました。
「地方創生」は非常に広いテーマであるため、まず学生グループは古平町の地域資源と地域課題について外部の視点から検討を開始しました。役場資料や議会記録の閲覧・分析や、古平町に出向いて行った関係者へのヒアリングや現地調査、関係者によるワークショップの開催を通じて、町の課題は、人口減少に加え、「古平町といえば○○」といったコンセプトが確立していないこと、町の創生に向けて努力している人は多いもののそれを束ねる調整役の存在が不足していることと考えました。そして、地域の資源として、中心産業である漁業、漁師町としての歴史や文化、関西電力が再エネ開発を進めていること等に着目し、これらの資源を活用して町の賑やかさを取り戻すことを目標に政策を練り上げました。
その際には、例えば「海業」を積極的に地域の力で推進する山形県由良地区や町の文化資源を町民自身で発見することで町への誇りや愛着を育む「宝探し」活動を行っている岩手県二戸市に担当学生が実際に出張してヒアリングや現地調査を行い、また、再エネの利活用に取り組む長野県飯田市や宮城県東松島市等の多くの関係者からリモートヒアリングを行うことで、古平町に活かせる部分を探しました。また、提言する政策には担い手が必要で、様々な他自治体の組織の体制や構造を調査し、持続性、自走性を確保した担い手となる組織の姿についても検討しました。
最終的な提言として、今は素通りしがちな観光客を留めることを重視した観光型の海業の提案、新たに生産される再生可能エネルギーを地産地消するための地域新電力事業、地域の遺産を探索する「宝探し」によるシビックプライドの造成とまちづくり・・という具体的な取組の内容を盛り込みました。さらに、これらの政策を実現するため、自走性を持ちつつ調整役としての役割も果たす、町民による協議組織と実行組織の設立を提案しました。
2025年2月には、検討成果を取りまとめた報告書を手に再び古平町に赴き、町長・副町長への報告会、地域のステークホルダーや関西電力も含む関係者の皆様への提案内容の説明会、お礼のための「鍋会」を開催し、多くの質問や意見が飛び交う場となりました。
この演習は、政策提言を行う際の一連のプロセスを現場で経験して肌で感じて自ら考えるとともに、古平や全国各地で地域課題解決に取り組む方々とも交流を持つことが出来た、貴重な機会となりました。
(担当教員:今井太志、中山隆治、山本直樹)
2024 年度 政策討議演習 (登別市班)
活動報告

2024年5月、登別市役所より、外国人住民が増加する中で、「多文化共生」を推進して「国際色豊かなまち」を実現するため、既存の多文化共生事業を踏まえ、新規の多文化共生事業を立案するよう、テーマが提示されました。
それを受けて、学生グループは、「住民の考える理想の多文化共生の在り方とはどのようなものであるか」、「登別市在住の日本人・外国人のうち、誰が、どのような多文化共生コミュニティ及びイベントを求めているのか」及び「外国人が必要としているサポートは何であるか」という3点のリサーチクエスチョンを設定しました。これに基づき、登別市役所、北海道登別明日中等学校、登別市連合町内会、登別商工会議所、介護老人保健施設グリーンコート三愛等の協力を得て、登別市在住の日本人及び外国人に対し、2024年10月~2025年1月の間、アンケート調査を郵送又はオンラインで実施するとともに、2024年6月~2025年1月の間、インタビュー調査を対面又はオンラインで実施しました。その一環で、3回にわたって登別市を往訪し、登別市在住の外国人を対象とする多文化共生事業の一つである「しょう会話」に参加するなど、現地で調査を実施しました。その結果に基づき、「コミュニケーション支援」、「意識啓発と社会参画支援」及び「地域活性化の推進やグローバル化への対応」という3点に関し、それぞれ課題を抽出しました。
これを踏まえ、学生グループは、2025年1月、学内報告会で意見を交換した上で、2025年2月、「北海道登別市における『多文化共生』の実現に向けて」と題する最終報告書を取りまとめました。その中では、「登別市に住む誰もがお互いに尊重して共に生きていく社会」に向けて、基本的なサポートに関し、外国人サポートワンストップ窓口に関するパンフレットの改善及びLINEの個人アカウントから公式アカウントへの移行、オンライン日本語学習教材の周知及び日本人を対象とする日本語ボランティア養成講座の開催並びにごみ分別を始めとする生活ルールに関する外国人向けのパンフレットの改善を提案するとともに、地域での交流に関し、モデル地区におけるイベントやコミュニティの開催及びその取組みのモデル地区から他地区への展開を提案しました。
これについて、学生グループは、2025年2月、登別市を往訪し、登別市長に提出するとともに、関係者に説明して意見を交換しました。
(担当教員:武藤俊雄、田中謙一)
2023 年度 政策討議演習 (栗山町班)
活動報告

栗山町の基幹産業である農業は、空港や大消費地札幌近郊といった地の利を生かしつつ、米・小麦・たまねぎ・種子馬鈴薯をはじめ多様な品種を幅広く生産しています。今後、栗山町の農業の持続可能性を担保する上で重要となる要素として、新規就農施策をテーマとしました。研究グループは、まず栗山町の農業に関する現状の整理を行いました。その結果、近年において農家戸数の減少が続いていることが確認できました。すでに2010年から栗山町農業振興公社で取り組んでいる新規就農者受け入れの効果もあり、周辺地域(空知)よりも農家戸数の減少率は穏やかであるものの、減少傾向が今後も続く場合、中長期的に農業の持続性担保を考えるならば、さらなる施策の拡充が求められていることが伺えます。
研究グループではこのような現状を踏まえ、既存施策と関係団体の活動をさらに詳しく調べた上で、現地の関係者に聞き取り調査を行って課題の洗い出しを試みました。具体的には、栗山町農業振興公社、栗山町地域おこし協力隊、栗山町新規就農者の方々にご協力頂きました。その結果、新規就農を拡充してゆくためには、就農施策をまちづくりと有機的に連携させてゆく必要があるのではないかという仮説に至りました。いわば、「栗山町の農業・まちづくり」という観点からの施策展開の必要性です。ここまでの分析を踏まえ、政策提言の方向性を次の三つに絞り込みました。①就農予定の方が、移住する前に感じる栗山町の魅力発信。②就農予定の方が、移住した後に感じる栗山町の魅力向上。③持続的に農業を続けることができる環境の整備。
政策提言の参考とするため、2015年に設立された農業組合法人である勝山グリーンファームを取材・調査しました。その結果、地域(勝山地区)全体で農業の危機感を共有することができている出発点から、売り上げ、収益金、後継者確保等の面で成果を上げるに至ったことがわかりました。
こうした調査分析を踏まえ、最終的な政策提言においては、農村RMOの導入(コミュニティ形成)、6次産業化の推進、技術力を高める研修支援制度の充実、農福連携の推進、という4つの柱で提案を行いました。これらを通じ、安定的な新規就農事業の展開と、持続可能な栗山町の農業実現を目指す提言となりました。2月にはグループメンバーが栗山町に出向き、町長に政策提言をプレゼンした上で意見交換を行い、町長からも実務の観点からすでに取り組まれている施策との関係でフィードバックを頂くことができました。農業の持続性確保という課題について、幅広い視点から、かつ、地域の実態に即した政策検討を行うことができました。
(担当教員:武藤俊雄、山本直樹)
2023 年度 政策討議演習 (斜里町班)
活動報告

2023年5月、斜里町役場より、「斜里町再生可能エネルギー導入戦略」に基づき、知床国立公園のゼロカーボンパーク登録を検討するに当たり、斜里町のゼロカーボンパーク個別施策を立案するよう、テーマが提示されました。これについて、学生たちは、「斜里町型循環共生圏」、すなわち、脱炭素化と地域活性化との両立を実現する社会モデルの構築が求められているものと受け止めました。
それを受けて、まずは、斜里町の行政計画、知床国立公園に関する先行研究、ゼロカーボンパーク及び地域循環共生圏に関する先行事例などを調査しました。その上で、2023年7月、斜里町を訪問し、知床国立公園など、現場を見学するとともに、斜里町長を含む斜里町役場、公益財団法人知床財団、斜里第一漁業協同組合、しれとこ斜里農業協同組合、ウトロ協議会、株式会社ゴールドウイン、知床斜里町観光協会及び知床ガイド協議会に対し、ヒアリングを実施しました。その結果、町に対する行政のマネジメント、町民と自然との関わり及び町と観光客との関わりという観点に基づき、関係者間の連携、環境配慮の動機付け及び情報の外部発信という課題を抽出しました。これを踏まえ、知床・斜里町ならではの環境・社会・経済にわたる循環共生圏を実現するため、環境配慮を目的とする地域内外参画型のプラットフォームをソフト・ハード両面で構築するような政策を提言することとしました。
その後、学生たちの議論を経て、2024年1月、学内報告会で意見を交換した上で、2024年2月、「北海道斜里町型循環共生圏モデル-脱炭素をテーマに人と人がつながる社会へ-」と題する最終報告書を斜里町役場に提出しました。具体的には、ソフト面では、知床を取り巻く多様なアクターによって構成される協議会を運営主体として、CSR・ESG経営を意識する企業を対象とする「知床型研修プログラム」を開発して提供するとともに、それに伴う関係者間の協働・交流の場となる「知床地域プラットフォーム」を形成するよう、提案しました。また、ハード面では、スマートフォンアプリやWEBサービスを通じ、地域における交通や観光について、情報を統合的に管理し、地域住民及び観光客に対して検索・予約・決裁を一括で提供するため、「MaaSHARI」と称するMaaSプロジェクトに取り組むよう、提案しました。
これについては、「広報しゃり」2024年3月号において、「知床国立公園のゼロカーボンパーク登録に向けて、外部から見る新たな知床の可能性を見出しました。」と評価されました。
(担当教員:中尾文子・中山隆治・田中謙一)
2022 年度 政策討議演習 (余市班)
活動報告

余市町担当班は、地域防災力向上のための広域連携をテーマとして政策分析、提言を行いました。2022年3月に、後志管内の余市町、仁木町、古平町、積丹町、赤井川村の5町村が、サツドラホールディングス株式会社、生活協同組合コープさっぽろ、ベル・データ株式会社と連携し、北後志広域防災連携協定を結びました。学生たちはこの広域連携の取り組みを研究対象として取り上げ、財政的、人的資源に制約がある地方自治体が地域防災力の向上を図るためのモデルケースとして、どのような連携のあり方が実効性を高めるために必要となるか、多角的に検討しました。
連携自治体5町村を手分けして訪問し、防災拠点施設を実地に調査し、それぞれの地域における防災担当者から防災体制の現状と課題意識について聞き取りを行い、北後志地域全体の課題構造の中に個別事情を位置付けて理解するよう努めました。その結果、人口減少と高齢化の進展という共通課題に加え、災害発生時の被災内容には相当な差があること、この点と関わって、行政の防災に向けた取り組みにも優先順位付けに差があることなどがわかってきました。民間事業者からも防災の実効性を高めるためのノウハウや技術の実装化、それらを踏まえた地域の将来像に関するビジョンも含めて調査聞き取りを行い、民間の力と自治体の政策をどのように組み合わせることが地域課題の解決につながるか、考えました。加えて、同じ北海道内で大きな自然災害に見舞われ、復興の取り組みを続けている厚真町、災害対応DXの先進地である室蘭市、広域防災行政の先行事例である関西広域連合等の取り組みからもヒントを得ました。
学生たち自身の調査を踏まえ、北後志広域防災連携協定の課題を、災害マネジメント、避難所運営、支援物資に係る業務、その他の4つに分類して整理し、それぞれの分野について、情報共有、プラットフォームの構築、共同計画の作成、住民参画という4つの切り口で提言を行いました。加えて、連携協定関係者間での認識の共有を一層進める必要があること、現状の連携範囲にとどまらずさらに連携の輪を広げることが防災力の向上につながると結論づけました。北海道に限らず全国的に少子高齢化が今後も一層進むことが予想される中で、自治体間の連携による課題解決は一層求められる時代が来ます。その点で今回の研究は示唆が多いものであり、学生たちの今後の研究や職業上での取り組みの発展につながるものと考えられます。
(担当教員:田中謙一、武藤俊雄)
2022 年度 政策討議演習 (栗山班)
活動報告

栗山町のハサンベツ里山では、20年ほど前から、地域住民のボランティアによって里山の自然環境保全の活動が行われてきました。しかし、現在、保全活動を継続する上で、活動を担うボランティアの高齢化、担い手・協力者の不足などの課題に直面しています。栗山町担当班では、栗山町役場からこれらの課題について提示を受けて、政策分析、提言を行いました。
栗山町を訪問し、実際にハサンベツ里山でのボランティア活動に参加するとともに、栗山町役場職員にインタビュー調査を行い、班員のブレーンストーミングにより、①行政と町民の意識の隔絶感、②誰が保全するか、関係者間の活動への意識の差、③組織や人、情報の連携不足といった課題があるとの仮説設定を行いました。
その後、ハサンベツ里山計画実行委員会、自然教育を行うNPO法人などにインタビュー調査を行うともに、栗山町民や学生に対するアンケート調査を実施しました。また、NPO法人キウシト湿原・登別など先進地視察もあわせて行いました。
その結果、①関係者間での定期的な協議の場を設け、里山のルールづくりを行うなどの組織と体制の土台固めを行うこと、②ハサンベツ里山のファンを増やす認知度向上の取組を行うなどの提言を行い、あわせて実現のためのロードマップを整理して提示しました。日本全国で、地域の活動の担い手の確保が課題となっている中で、今回の提言は他の自治体でも参考となる意義のある内容となりました。
提言作成後、栗山班員が栗山町長と教育長に対してプレゼンを行い、率直な意見交換を行いました。今回の授業を通じて、仮説設定、現地でのインタビュー調査やアンケート調査、先進地視察を行った上で、班員間での議論を踏まえた政策提言を行うことができ、社会人学生にとっても、これから就職を目指す学生にとっても、自治体の地域独自の政策課題に現場で真剣に向き合う貴重な経験となりました。
(担当教員:中尾文子、山本直樹)
2021 年度 政策討議演習 (余市班)
活動報告
 公共政策大学院と余市町は、2021年3月に包括連携協定を締結しています。
公共政策大学院と余市町は、2021年3月に包括連携協定を締結しています。
余市町においては、現在、ワイン用ぶどう栽培農家は50軒近く、ワイナリーも15軒を数え、全国でも有数のワイン産地となっています。ワイン産業を活用した余市町の活性化をテーマに学生たちは検討を開始しました。
まず、余市町の複数のワイナリーを訪問して取材するとともに、北海道内外のワイン産地の振興策について、文献や地方自治体への書面取材等により調査し、参考となる先進事例の整理を行いました。
さらに、余市町では、ワイン産業以外に果樹・漁業も盛んであることや、観光振興に課題を抱えていることに着目し、果樹農家・農協・漁協・観光協会・商工会議所・青年会議所・宿泊業者・飲食業者・酒販店・地域交流団体などにも取材を行い、余市町の豊かな資源をフルに活用した地域活性化策を検討することにしました。
こうした地道な現地調査の結果を踏まえ、学生より、『「食と酒のまち余市」に向けて―地域連携プラットフォームの提案―』と題して、余市町への政策提言をまとめました。提言では、ワイン産業の振興に加え、地域の産業を構成する様々な団体・事業者が地域活性化のアイディアを出し合うプラットフォーム(交流の場)を設けることや、アイディアの実現に向けたプラットフォームの具体的な運営方法や行政の支援のあり方などについてまとめました。提言の作成にあたっては、取材を行った団体・事業者に案を提示してさらに意見を求めたり、同様の仕組みを設けた他の地方自治体にオンラインでインタビューするなど、より実現性の高い内容となることに努めました。
提言をまとめた後、余市町役場との共催で地域住民向けの説明会をオンラインで開催するとともに、齊藤啓輔町長に面会し、役場職員の方々も交え率直な意見交換を実施しました。のべ十数回にわたる現地取材による現状と課題の把握、先行事例の調査・分析、町長や地域住民へのプレゼンテーションなど、学生にとって貴重な経験となりました。
(担当教員:中園和貴、中尾文子)
2021 年度 政策討議演習 (芽室班)
活動報告
 芽室町議会は、2013年に議会基本条例を制定し、これまで、住民参画、情報共有などに関して様々な取組を行ってきました。芽室町の議会改革は全国から注目されており、高い評価を受けています。一方で、近年、議員選挙の投票率が低下するなど、芽室町民の議会・議員への関心・期待は必ずしも高いものとはいえない状況にあります。そのため、芽室班では、町民が理解しやすい議会活動に対する評価方法はどのようなものかをテーマとして、検討することとなりました。
芽室町議会は、2013年に議会基本条例を制定し、これまで、住民参画、情報共有などに関して様々な取組を行ってきました。芽室町の議会改革は全国から注目されており、高い評価を受けています。一方で、近年、議員選挙の投票率が低下するなど、芽室町民の議会・議員への関心・期待は必ずしも高いものとはいえない状況にあります。そのため、芽室班では、町民が理解しやすい議会活動に対する評価方法はどのようなものかをテーマとして、検討することとなりました。
芽室町を訪問し、議員だけでなく、芽室町の中高生、子育て世代、NPO活動に従事している方など、様々な町民に対してインタビューを行うとともに、先行事例として、情報発信に取り組む登別市議会や、若者の意見を取り入れる少年議会に取り組む山形県遊佐町議会を訪問し、調査しました。
芽室班では、これらの調査で得られたデータに加えて、市民参加やプロジェクト評価に関する理論などを活用して、検討を進めました。その結果、議会の役割について町民の理解が不足している、議会活動に関わる情報が効果的に町民に提供されていないなどの課題を踏まえて、評価手法だけでなく、成果を明示した上で必要となる活動を提示し、議会活動による町民の変化を指標として評価する、一連の具体的なプロジェクトを提言しました。提言の中には、議会のトリセツの作成、少年議会の開催、議員単位のホームページの開設など、具体的な活動例も盛り込みました。
提言作成後、芽室班員が町名産のピーナツのオリジナルTシャツを着て、芽室町議員全員に対してプレゼンを行い、率直な意見交換を行いました。現地でのインタビュー調査、先行事例の訪問調査、班員間での徹底した議論、学術的な理論を活用した分析に基づく取りまとめなど、理論と実践の双方を重視した授業を実現することができ、班員にとって貴重な経験となりました。
(担当教員:山本直樹、武藤俊雄)